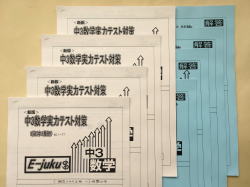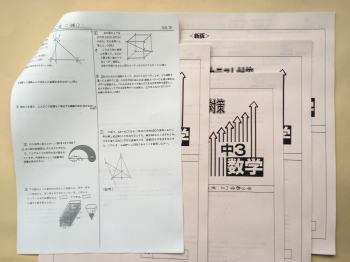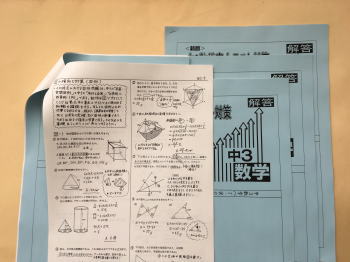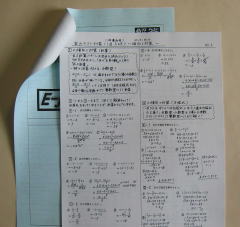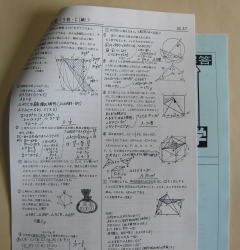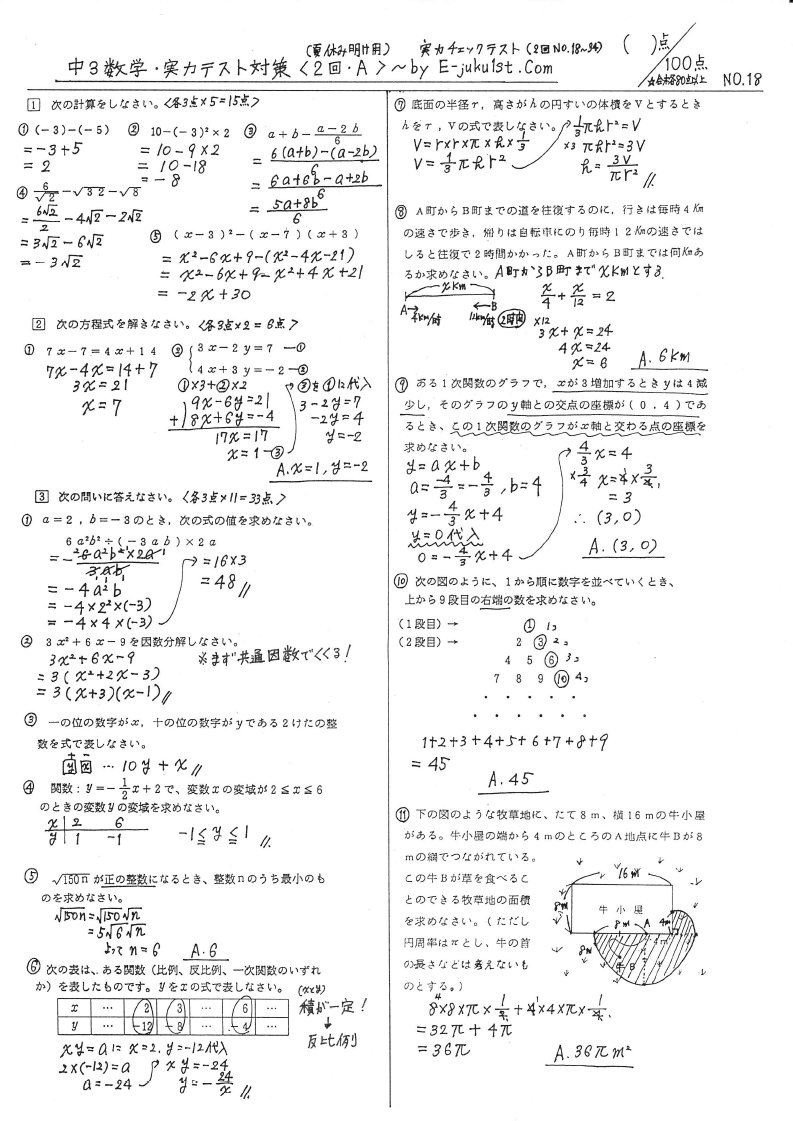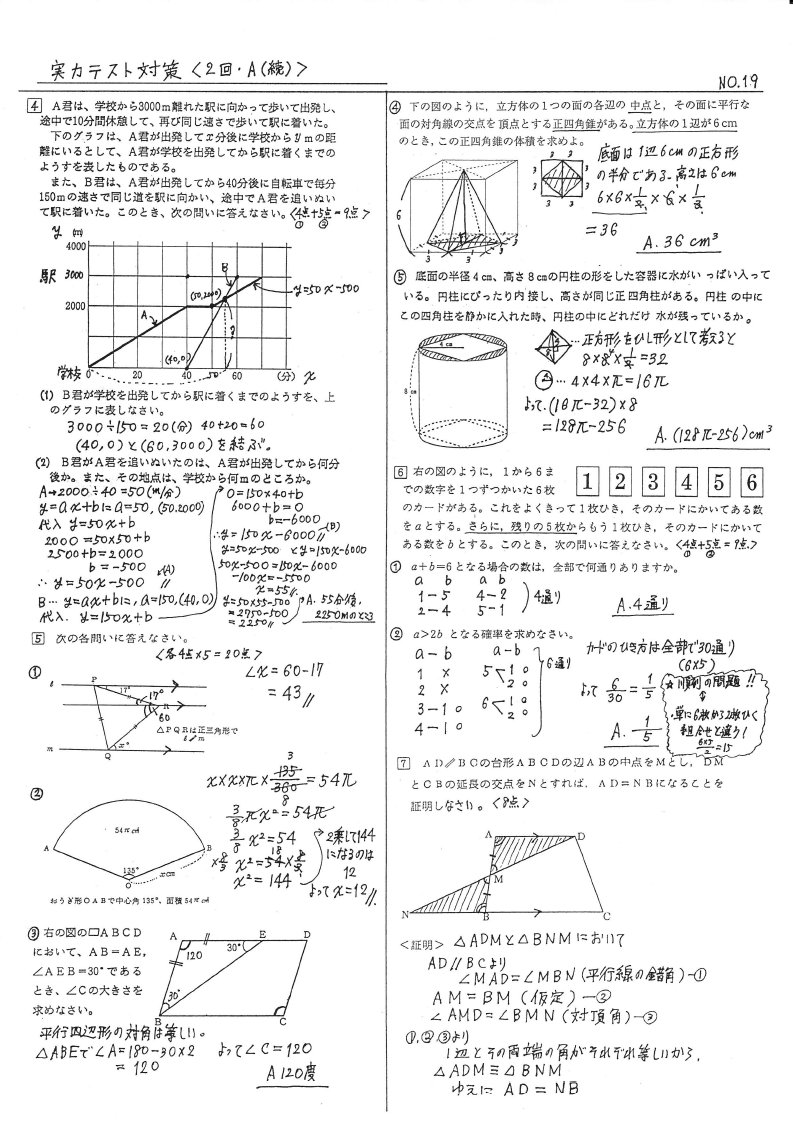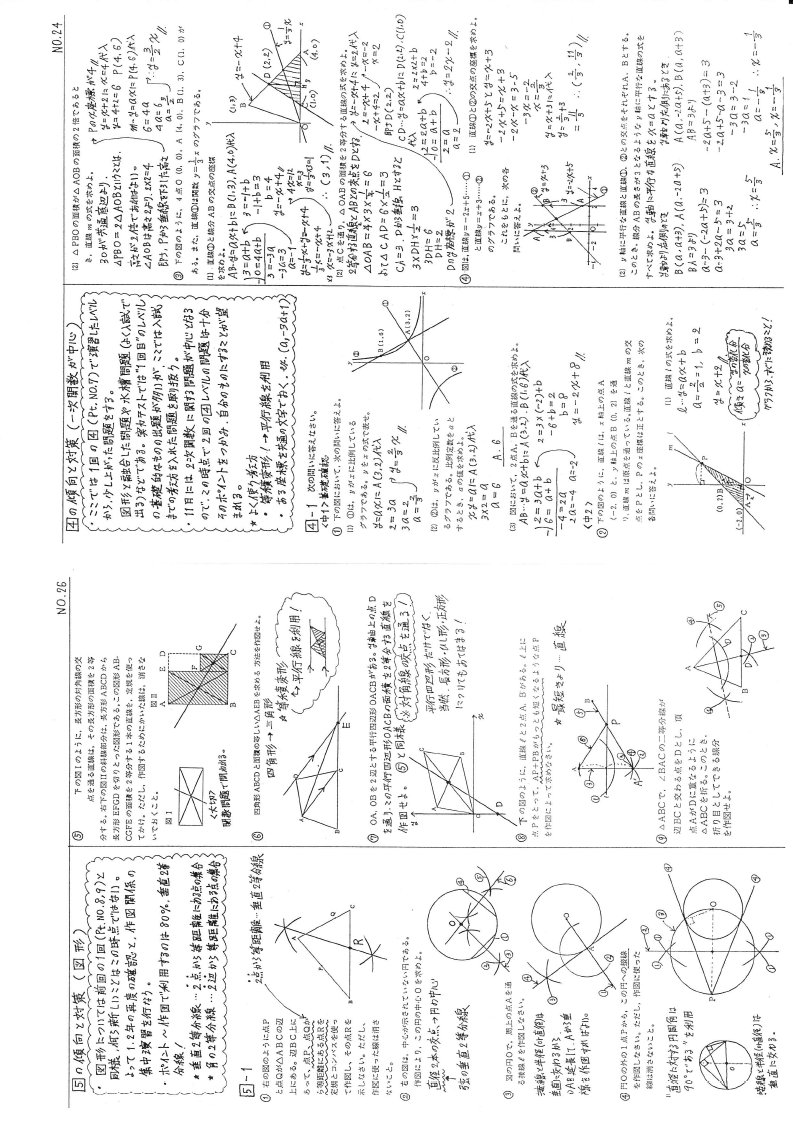|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別掲載(2025年5月11日配信のメルマガより)〜期間限定〜 |
| 1.E-juku1st.Com の情報 NO.937 ================================= 理解と暗記について VOL.1&2 <理解を支え、持続させるのは暗記> ================================= <勉強には「理解」と「演習」と「暗記」>VOL.1 理解と暗記について、今回述べてみます。 勉強していく上において、理解をするのは基本です。こんなことはわたしが書くまでもなく誰だってよくわかっていることです。 では、理解したから問題が解けるのか、理解したから暗記も深くなるのか、理解したことはすべて実力に繋がるのか――。 ここがですね、一般にはどうもさまざまな問題点と、また誤解を含んでいるように思います。 新しいことを習う。しかし、これも厳密にいえば、ほんとうにそれまで知らなくまっさらな状態で習うものもあれば、過去に習ってきたものを踏まえて、幅を広げあるいは深さを増して習う内容のものもあります。まあこれは余談ですが、この前者の割合が多く後者の割合が少ないのが、一般に、小学と中学の学習のあいだの関係であり、前者より後者の割合がぐんと多くなると感じるのが高校での学習内容でしょう。そしてその学習量と知識量、難度や消化スピー ドの違いなどにより、かなり面食らう(?)のが高校の授業です。 話を中学段階に戻しますが、この新しいことを習うに際し、昔の授業でわたしらが学習した行為は、あくまで授業の「説明」を聞くものであって、「理解」と「暗記」は自分でするものだ、という意識と態度がすくなからずその根底にあったように思います。もちろんその説明の背後には、教師による生徒への理解のさせ方や指導上のみえぬ苦労は多々あったにしても。 その「理解」と「暗記」が自分でじゅうぶんできない生徒は成績が悪く、じゅうぶんできる生徒は成績がよい、という単純な図式があっただけです。それがいまや、学習内容が中学でもずいぶん減らされたにもかかわらず(注:数学と理科は、ゆとり教育の揺れ戻しで増えました。しかし、それでも昔と較べるとまだまだ少ないです)、生徒の理解力は低く暗記力も弱くなっている現実に首をかしげているのは、わたしだけではないでしょう。 ところが、一方の現実は、学校でもテレビまたネット上でも先生が生徒に教えている場面に出遭いますと、それは不思議なことに国語ではなく理科でも社会でもなく、算数または数学の授業になることが圧倒的に多いでしょう。その授業のねらいは、生徒にいかに「理解」させるか、この一点に集約されているかにみえます。理解に重点とすべての価値を置き、まったく不必要と思えるほどていねいに説明をし、生徒に考えさせる時間をずいぶん多くとっています。 さらにいまの生徒の多くは、学校の授業以外に塾に通って勉強をしているわけですから、当然そこでも新しいことを習うに際し、単なる説明ではなくあれこれポイントやコツを教えてもらい、また理解させてもらっているわけです。 学校では十二分に考えさせられる時間を与えられ、新しく習う基礎の知識の理解にこれでもかというほど重点を置いた授業を受ける。塾では十二分に考えさせられる時間はないにしても、その代わり、同じ内容の理解をポイントやコツを交えて教えてもらい、効率よくそして要領を得た知識をつけてもらうことになる。 それゆえ、授業を受けたその場では、生徒本人は理解したと思うのは当然であって、新しい内容の問題をすらすら解くことができるのはなんら不思議なことではありません。ここに、ひとつの落とし穴があるのではありませんか? つまり、本人は理解したと思っているから。この意識と感覚で勉強を進めている生徒が、いかに多いことか・・・。しかしその理解の姿と内容は、自分の頭を痛めて考え奪いとったものではなく、ただ手を前に差し出して、たまたまそこに載せてもらったに過ぎないものだから、すぐに手の指のあいだから落としちゃうんですね。 こんなんでたとえ定期テストレベルではいい点数がとれたとしても、あくまでそれは基本のレベルの問題に対してであり、それですら時間がたてばあっという間に磨り減って、学力が凋んでしまう生徒はほんと後を絶たないでしょう。 1,2年のあいだの実力テストというものの正体は、まだ基礎と基本的な知識を連結あるいは寄せ集めたに過ぎない。それでもふだんのテストよりガクンと成績が下がる生徒の多くは、その大きな原因として、「理解する学習とその周辺」にとどまっているだけではないか、とわたしは分析している。 「理解したから問題が解けるのか、理解したから暗記も深くなるのか、理解したことはすべて実力に繋がるのか」 と、上述しました。この3つを別けていうと――。 理解したから問題が解けるのか、がはっきりするのは、習ったそのときではなくて、だいぶ時間が経ってからのことでしょう。 理解したから暗記も深くなるのか、は一般の常識(?)と外れて、関連性は思うほどないよ、と思っています。 理解したことはすべて実力に繋がるのか、もまったく生徒の勉強の姿、現実を観ていない問いにすぎない。 理解は勉強の目標でも中心事象でもない。ここでは小さく、狭く限定するが、勉強の目標は一度習ったことはすべて覚えてしまい、その知識を実力として蓄えることである。1を習えば1を、5まで習えば5の力を、10まで習えば10の力を、そして100まで習えば100の実力を有することである。そういう実力を備えていくには、「理解」と「演習」と「暗記」の3つの学習をじゅうぶん意識して積んでいくことだろう。またこの3つをセットにして学習していかなければ、その学力はじゅうぶんなものは得られない、と思って間違いない。いずれのひとつが欠けても、いずれのひとつが弱くても、まともな実力は形成されないのである、とほぼ断言しておきたい。 このことは、5教科すべてについていえる。いまの学校の授業内容というものは、あらく表現するが全体を10とすればそのうち6,7の割合が「理解」に費やされ、残り3,4の割害が「演習」にまわされているのではないだろうか? それにも関わらず、応用ではなく基礎の理解すらできていない生徒、時間が経つと基本の知識すら抜けて忘れてしまう生徒、あれほどしっかりと理解はしていたはずなのに問題の解き方や注意点がぼやけて自己流になったり、雑になったり、そして同じミスを何度も繰り返したりする生徒など、その現象と度合いはまちまちながら、いずれの場合もまともな実力形成は為されているとは決していえず、これらすべて含めると、その割合は半数どころか軽く4分の3を超えている。 ここでは教える側の問題点と欠陥、そして改善すべき点を指摘しても(大いに指摘したいが)なんら有用性はないので、学ぶ側のそれらを指摘するが、いや、すでにじゅうぶん明記しているのだけど、もう一度言及する。 勉強には「理解」と「演習」と「暗記」の3つの容が伴っていること。いずれかひとつ欠けても、いけない。いずれかひとつ不満足なものがあってはいけない。わたしの場合、これら3つを同等に扱っている。でも、数学と英語では違うでしょう、理科と国語では違うでしょう?――。いいえ、同じです。どれが欠けても成り立たない。まったく同じ価値です、とあえていいたい。 では、生徒の勉強で欠けているものとは、なにか? それは、「演習」と「暗記」でしょう。ただし、「理解」も実は、足りない。理解は、ほんとにやさしいことは除いて、初めに一度だけでできるものではないでしょう。つまり、初めに人から教えてもらってわかる理解はまだ薄っぺらなもので、まだ自分のものにほんとうになっていないところがたぶんにあり、自分の頭で再度考えることが大切でしょう。さらに演習を通して知る理解、徐々に深まっていく理解もあります。また暗記をしてる最中に、新たに得る理解だってなかにはあるんです。新たな内容の初めにだけあると区切らないことが大切なんです。 さて「演習」と「暗記」。 演習している量、これがやはりまだ全般に不足しているように思います。ただこれは、絶対基準というものがなく、生徒の能力によってどこまで増やせばいいのかという単純な図式はなく、それ以上に、その演習を通して生徒が何を学ぶか、学び取るか、その目的意識と作業のなかの集中度や取り組む姿勢にこそ直すべき課題があるのであって、共通した土俵では言えないところです。また単純な繰り返しだけでもダメで、絶えず考えながら問題にあたるという、そして基礎からある程度応用までを含んだ問題構成のなかで演習するという、そういう環境が与えられた問題集(ここですみません、宣伝。E-juku1st.Comの問題集はすべて、この点に留意して作ってあります。失礼いたしました)で、勉強するのが望まれます。これらの条件と状況を踏まえた上でもなお、演習している量が、多くの生徒にはまだ不足しているのは否めないところでしょうか。 最後に「暗記」。 実はこれが今回、もっともいいたい点、主張しておきたいことかもしれません。いまの小・中では「理解」が主役で、「暗記」は脇役どころか日陰に追いやられているような、存在の薄い印象を受けますが、これをもっともっと大事にしてもらいたい、そして真剣に取り組んでもらいたいと思っています。わたしの想いで書きますと、学習全体(10として)、いや実力をつける勉強の中身全体でいいますと、「理解」:「演習」:「暗記」=2:4:4の比重くらいになります。 ネット上の或る記述に、次のようなものがあります。学校でも塾でも問題集のなかの説明でも、このように考えている人は主流かと想われますので、その一例として。 「繰り返して練習するよりもさらに忘れにくい方法、それが『理解する』ことです。そのためにただ暗記するのではなく、常に「なぜ?」そうなるのかを考えるようにしましょう。理由がわかれば「なるほど!」と納得できます。このように納得して憶えたものは単純な暗記と違って 忘れる率が大幅に低くなります。特に中学生から高校生にかけて脳の発達段階が単純な記憶から理解し納得する記憶へ移行して行く時期なので、理解し納得する学習は非常に合理的で効果のある勉強法なのです。 さらに、丸暗記は単純でつまらない作業ですが、理解し納得する学習が身につくと達成感があって勉強の面白さがわかってきます。」 まあアホらしくて、まともに語る気にもなれないのですが、そこはぐっと我慢し、もうすこし書き進めてみます。 この人は理解することが忘れにくい暗記の方法だと書いています。なぜそうなるのか、常にその理由を考え、なるほどと納得し理解したものは、非常に合理的で効果のある勉強法だ、とも書いています。 しかしこれは、勉強の入り口の論理で、理解するなんてことは、勉強する上において当たり前のことでしょう。理解したそのあとの結果は、どうなんだ?! 理解することが忘れにくい暗記の方法なら、生徒はみな、中3の実力テストで平均点が45点になるようなひどい点数をとらないと思うけれどね。 また、なぜそうなるのかを常に考えることはとても大切ですばらしいことだが、それが合理的で効果のある勉強法である実証はなんら示しえていない。わたしのお粗末な体験からいっても、それはいっさい見い出しえない。勝手な理想や理屈を抜きにしてあくまで現実のなかで捉えるけれど、いったいどのくらいの生徒がこれをやっているのか。というより、こうしたことをなしえる能力と余裕が生徒にあるのかを、この者は果たしてどれほど「理解」、知悉しているのだろうかと、むしろ根本的にこの認識力を疑う。 中学生から高校生にかけて脳の発達段階が単純な記憶から理解し納得する記憶へ移行して行く時期というのも、どうも半分ほどの事実しか押さえていないのではないか。 高校でいうなら、われわれは、たとえば英単語や熟語、構文まで、どれだけ単純な記憶をしなければならなかったか、ちょっと憶いだせばすぐにわかるだろう。日本史世界史の事象、年代の暗記、あれを理解し納得する記憶と呼ぶのだろうか。まだまだあるがやめておきます。つまり、両方の記憶が要るんです。物理や化学、自分でいうのもなんですが、まあ得意でした。しかし、相当に理解し、努力して納得し暗記もしました。でもですね、その数々の理解や納得はどこかにキレイさっぱり吹っ飛んでしまって、わたしなんぞいまやその残滓も残ってはおりません。 <理解を支え、持続させるのは暗記>VOL.2 丸暗記は単純でつまらない作業と書いておりますが、果たしてそうか?! 「暗記」のなかのひとつして「丸暗記」があるかと解釈しますが、この言葉には負のイメージのレッテルが貼られていて、たとえばテスト前の一夜漬けのようなその場しのぎの勉強がイメージされるので、これをまったく否定するつもりはわたしにはありませんが、あくまでわたしの使用する暗記は、それ以外のふつうに行われるさまざまな暗記と捉えていただきたい。 ‘暗記’は単純でつまらない作業です。この文章で正しいのは、‘暗記’は単純で、までであろう。単純であるがゆえにつまらない、と思うのは、もちろん自由だけど、単なる主観であって、この主観の位置にあえて立てば、わたしは‘暗記’は単純だけど別にキライではない、むしろ好きなほうかもしれない、となるかな。 世のなかには、わたしらが一見単純でつまらない作業に思えるようなことを気の遠くなるほど延々と続けて、また積み重ねて、その規模の大少関係なく壮大にものをあるいはほとほと感心する作品を創りあげる人が、多数いますよね。 人体に悪い影響を及ぼさないため化学肥料をあまり使わず、そのため腰を屈めて採っても採っても毎日のように伸びる雑草と格闘し続ける農家の人の話。これを単純でつまらない作業とは誰も考えない作業もあるでしょう。単純な実験と調査を数年も繰り返してやっと製品化にこぎつけるものもあるでしょう。このようなことをちょっと思い浮かべればいくらだってありそうですが、そもそも我々の日々の生活のなかですら、食事作りから掃除、洗濯、その他家事全般、単純といえば単純、しかしほんとに大切な作業の繰り返しをつまらないとは思わず(ときに思うことがあっても)、ふつうにまた懸命にやっていることでしょう。 ゆえに、というわけではありませんが、そんな道理を書くまでもなく、‘暗記’を単純でつまらないと感じるのは、勉強に手間と時間をかけたくないだけの単に甘ったれた感情の部分が大きい、とわたしは思っています。もし単純な作業をつまらないと思うなら、勉強だけではなく多くの仕事にも上面だけなぜてその大事さに気づかないことになるだろう。 さて、「この文章で正しいのは、‘暗記’は単純で、までであろう」と書きましたが、ほんとうのところ‘暗記’は単純で、とは考えていない。よしんば単純であっても、そこにいろいろと工夫をしたり、気分の転換を図る術を採り入れたら、ずいぶん面白く取り組めるのだ。新しいことを理解し、納得することだけが、勉強の面白さではない。 そこを教えたり実際の学習のなかで折に触れてアドバイスをしたりする教師はほんとに数少ないだろうし、また期待することも難しい。その具体的方法(即ち、奇抜なものではなく平凡なことです)を2、3例を挙げてみてもほとんどたいした意味はない。なぜなら、たとえわかったとしてもやるかどうかは本人次第であろうし、勉強に手間と時間をかけるという当たり前の心根、気持がまずその根底にあって成り立つであろうから。つまり、生徒自身が自分に適ったものを見つけ、改善と工夫を積み重ねて実践していくことが、なにより求められるのでしょう。 これができないから、またはわかっていないから、勉強のしかたをどうすればいいかとか、効率的な勉強のしかたやコツを教えてほしいとか、そんな大まかで実は捉えどころのない空虚な質問を、中3になっても(高校生でも)平気でネット上に溢れるほどしているのをみるけれど、嘆かわしいといわざるをえない。 上のVOL.1で学習全体を10とした場合、ほんとうに実力をつける勉強のあり方でいうなら、「理解」:「演習」:「暗記」=2:4:4の比重くらいになると書きました。しかし理解を支え、持続させるのは暗記でしょう。これがわかっていない。演習のなかでも暗記は深めていかねばならない。これもわかっていない生徒は多い。暗記のための暗記もときに泥臭く無心にしてゆかねばならない。3つの学習に跨って、暗記は学習全体を支えているのである。その結果持っている力が、実力でしょう。 以上、今回述べた内容が、学習を進めていく上でのなんらかのヒントまたは反省を加える視点の材料にすこしでもなればさいわいとするところです。 |