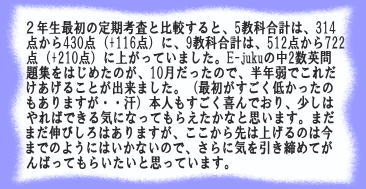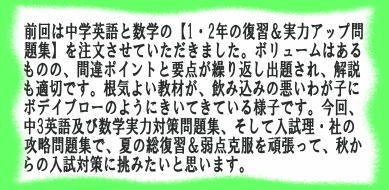|
||||||||||||||||||||||||||||
| ◆◇●○ 問題集ご利用者の声・お便り ○●◇◆ |
| 問題集をご購入いただいた方からの声とお便りは現在560あまりあるのですが、あまりに多いのでここではそのなかから45ほど、下の区分で選び掲載しています。もしよければご覧ください。クリック |
| ▼ 高校入試でターイセツなこと、って何だ?! ▼ |
| §39定期テストの点と実力テストの点 <定期テストの点と実力テストの点がなぜかくも違うのか?> 中3生で話します。 (中2生生は右のブログ(NEW)のほうが向いています。) 中3一学期の中間テストの合計点が、410点(数学91点、英語82点、国語73点、理科88点、社会76点)のA君。まあまあ頑張っている成績ですね。クラスのあるいは学年のトップ生は465点前後(中には、480点以上のケースもありますね)をとっていると想われますが、おおよそこの成績では、クラスの5,6番といったところでしょうか。 もう一つ例をあげましょう。やはり中間テストで合計点が436点(数学88点、英語95点、国語82点、理科78点、社会93点)のB君。部分的に見れば課題もありますが、全体的な印象ではとてもよい成績です。クラスで3番くらいとします。本人も親御さんも他の生徒からも、また先生からもよくできる生徒と見られています。 次に、期末テストがありました。その結果はA君、425点。B君は、440点。2人とも順調です。よく頑張っています。 さて、夏休み明けの実力テスト(中3では、第2回かな)がありました。 A君の結果-数学76点、英語72点、国語65点、理科80点、社会71点-合計点364点でした。 B君の結果-数学72点、英語78点、国語66点、理科58点、社会67点-合計点341点でした。 うん!?・・・いったい、これはどういうことでしょうか? まず浮かぶのは、夏休みの過ごし方とその勉強でしょうが、ここではその要因はあえて排除します。どちらもふつうに努力し、勉強したとします。では何故、こういうことが起こるのでしょうか。 A君の方がB君より成績が上になってしまった。これは特殊なケースなのでしょうか? いえいえ、これはよくあるケースなのです。A君も点数は下がっているのです。定期テスト(期末)から61点もダウン。B君の方はなんと99点もダウンです。 一般に、中3ですから平均的な生徒の定期テストを350点としますと、実力テストの成績というものは、100点ダウンの250点前後になるのがふつうです。ですから、B君の99点ダウンの341点は至極当然の結果である、といえなくもありません。ただしそれは、成績中位から下位の生徒の傾向と現実であり、7割ぐらいの生徒に当て嵌まる現象です。成績上位者も確かに点数が下がるのですが、その下がり方は上になればなるほど少ないのが一般的傾向です。つまり、B君の例でいいますと、多くても50点ダウンの390点から400点ぐらいはすくなくともとっておかねば、おかしいわけです。 B君の落胆、塞ぐ姿を想像するのは容易です。友人や親からの励ましもあるでしょう。優しい先生なら「心配するな。今度頑張ればいいから。」という言葉もあるかもしれません。本人も、こんなはずはない、たまたま体調が悪かった、あるいは時間以内に問題全部解けなかった、と自己分析してるかもしれません。 しかし、もしそう考えているのならおかしいし、判断が間違っています。もしそう考えていないのなら、では、どう考えたのか? 塾に行ってるなら(7,8割はすくなくとも通ってますよね。)、学力テスト(模試)があるわけです。自分の学力をもうある程度知ってるはずなのです。しかしながら、塾に行っていても自分のほんとうの学力を直視していない、また認識しきれていない生徒も案外いるのです。ただ、ここでは通塾の有無は関係なしとして話を続けます。 さて、ここに大事な何かが欠落しています・・・。 ところでその前に、クラスのトップ生の成績はどうでしょうか? 気になりますよね。定期テストでは450点から470点くらいとってる生徒です(<注>ただし、この中学のテストの作りは、やや難しい目とします。わたしの問題集を利用している生徒のなかには、ほんと感心することに、平気で470点やそれ以上とっている生徒もなかにいるもので・・・)。 中間テスト467点、期末テスト456点としましょうか。(すみません、成績上位の生徒の話ばかりになって。でも、なんらかの形で、この指摘や問題となるところが当て嵌まったり、参考にできる点があろうかと思います。) クラストップ生の実力テストの成績結果-数学88点、英語92点、国語80点、理科86点、社会90点-合計点436点でした。 適当に点をつけてるのではないですかって? はい、適当です。 実力テストの中身もレベルも知らないで、とお思いかもしれませんが、公立中学の実力テストの内容と形式は、これでも熟知してるつもりです。ひと言でいうと、これは過去の経験の寄せ集めです。特に難易な、あるいは独創的な形のテストではありませんから。20年あまりの塾直接指導の経験と分析から申し上げています。誤差は多くて5パーセント未満と思ってください。 成績一番の生徒の成績ダウンは、25点です。なかには、通常のテストの成績よりも上の点をとる秀才も稀にいますがそれはさておき、定期テストのB君と一番の生徒の差は、期末テストで16点なのに、実力テストの差はなんと95点にもなります。すごい差です。 ここでひとつ、はっきりしましたね。ふだん見えてるようで見えていないものが。 ---そうです、実力です。実力の差です。残念ながらB君には、実力がかなり不足しているのです。これでは志望している公立高校には内申点的には足りていても、実力的にはかなり無理があるといえます。 このことを、本人と塾と学校の先生がしっかり認識しているか、また把握しているか? 本人はもちろん、塾の先生や学校の先生がもしきちんとふだんから、実力の把握とその対策(これは言葉でいうのは簡単ですが、ホント難しい。)を行っているか、実力養成の問題を適切に指導しているか、そして生徒が学んでほんとうにそれらを吸収しているか、ということがとても大事なポイントとして指摘しておきます。 次に、もうひとつ実力テストの点数で見ておきましょうか。B君の欠落してる部分です。 それは、各科目の点数にあります。数・英・国についても少しずつ点数が足りません。が、それ以上に理科と社会に問題があります。まず社会、定期テストではA君は76点、B君は93点、一番の生徒は上記には書いてませんが94点としましょう。それが実力テストでは、A君は71点、B君は67点、そして一番の生徒の点数は90点という結果です。B君は得意なはずの社会でも、一番の生徒に大きく差をつけられ、A君にも負けています。こんなことが起こるのか、ですって? はい、しょっちゅう起こるのです、別に稀なケースではありません。 こわい現実です。で、その原因は? 答えは簡単です。忘れてしまったのです。それもややこしい細かいところではなく、覚えていて当たり前の基本的な知識があちこち抜けてしまっているのです。 お気づきの方も多いでしょうが、中3なら社会は公民分野の勉強になります。定期テストは狭い範囲からの出題ですから、先生の授業をしっかり聞いて、真面目に努力していれば93点といういい点もとれるでしょう。とても頑張ったわけです。それに対して実力テストは、中1の地理、中2の歴史、中3の公民からの全出題です。実力テストの平均点は、50点(実力テストの社会はそんなものです。)とします。それと較べるなら、67点はあまり悪くはないのですが、もし公立トツプ高を狙うつもりでいるのなら、とんでもない学力といえます。要するに、習った全範囲に対する実力が根本的に不足してるのです。つまり、これまで深く長く記憶するといった勉強のしかた、あるいはそれ以上に、反復して覚えるといった復習の勉強をしてこなかったのです。 次に理科。もうこれは分析するまでもありません。本人の点数は58点、おそらく平均点は45、6点前後と思われますが、平均点よりややいいという点数・・・。平常のテストの点も他の教科に比べ低いですし、はっきり実力も低く危うい。 では、どうすればいいのか。 あきらかに、まず勉強してきた範囲の、徹底した復習の勉強でしょう。一からやり直しです。(できることなら、もっと早めに、自分の実力に目をそらすことなくきびしく見つめて、そして復習を大いに心がけて実践していれば、こういうことにはなりません。) ところで、B君中心に話が進行しましたが、A君のほうはどうなっているのか。 A君の成績を分析しますと、まだ伸びる余地はありますね。国語はこの時期(中3の2学期)ともなると、もうあまり期待できないかもしれませんが、英語と社会に焦点を当てればもっと実力が上がるはずです。ただ、かなり勉強しても2学期の定期テストの点が450点とれることはきびしいかもしれません。しかし、1,2年の復習と受験問題に力を入れれば、実力テストの点数アップは、まだそこそこ望めるはずです。 しかしですね、本人の努力と成績アップにもかかわらず、「内申的」には評価はあまり変わらず、思っている位置には届かないかもしれません・・・。なにもわたしがこのようなこと、書きたいわけでは決してありません。過去幾多とこういうケースを見てきたからこそ、ひとつの注意点として知っていてほしいと思います。成績と内申点が、単純明快に比例していてくれれば、とてもうれしいことです。しかし、現実は一部を除いて、異なってしまうケースが多々出てくるものです。 中3のそれも後半にもなって、こうしたことに気づくなんてことは、絶対避けるべきだと考えます。いまのうち識って置いて、できるだけ対策を打ってください。おそらくこのブログをお読みいただいている方のなかには、中1あるいは中2生をお持ちのご父母の方、また中3生でも時期的にも間に合う方も多くいらっしゃるでしょうから。 |
| 特別掲載(2025年2月26日と3月5日配信予定のメルマガより)〜期間限定〜 |
| ================================= 1.E-juku1st.Com の情報 NO.931 <やる気について> ================================= <ただ「習慣」である> 今回は、「やる気」について・・・。 これはへんに色気を出して論理的に書こうなんて気をもし起こすと、とんで もない迷路に嵌りこみそうな話題であると感じています。かといって、そぞろ 気が向くまま書こうものなら、元来気は長いほうではないので、「やる気がな ければやめておけっ!」って、叱阿する言葉がつい出てくるであろうし、話題 の展開もヘチマもなくなるのがおちであります。だから、そのあいだを往くこ とにします・・・。 英語のmotivateは、「人に動機を与える、学習意欲をそそる、〜にやる気を 起こさせる」という動詞形ですが、その名詞、モチベーション(motivation) とはご存知のように、「動機づけ・意欲・やる気」という意味になります。英 語で表現すると、なにか人為的にまた作為的に、ある方法や手段によって、 「人にやる気を起こさせる」ことがなんでも可能なように思わせがちなのです が、そしてその理論や実践は、経営学的にさまざまに構築され運用されている のも事実でありますが、しかし、それが仕事の場ではなく勉強の場となると、 さてどうなんだろうか?・・・――― 英語やカタカナで表記するとある種、情念が入り込まないというか軽さがあ り、それ以上思考が進まない面があります(うーん、わたしだけか?・・・)。 一方、「やる気」なんて日本語になると、もうもろに自分の内部にある感情と 気分ですから、象はないけれどいまにもすぐそれとコンタクトがとれそうにも 思てしまいます。が、しかし・・・。 ・「やる気を出すにはどすればいいですか?」 ・「今、全然やる気が出ません。もうすぐテストがあるんですがすぐにやる気 が出る方法はないでしょうか?」 ・「どう頑張ればいいのか、何をしたらいいのか、まったくわからず自分でも 困っています。勉強をする気になれません。何もしたくありません。でも何 かやる気がでるような良い方法はないでしょうか」 このような生徒の質問がネット上に載っています。それに対して、世間には 奇特な方がずいぶん多くおられて、まことに丁寧というか親切な回答がされて いるのに出くわします。それが飽きもせず繰り返されている現象に、わたしは 閉口して、いまはまったく見ないようにしています。ネット上の「質問」とい う名の得たいの知れぬものは、パンドラの匣をあけてしまったかのように、も うなんでもありです。 もちろんこの感懐は少数の者が抱くでものであろうし、それらの応答を排斥 する意図はありません。ただ、否定はしたい気分ではあります。こういう個人 の感情に属するものに、それも恣意的な気分に属するものまでに、見境なく答 えや方法を質問する、そのあまりにも度が過ぎた依存心と幼稚さは、いったい どうやって生まれたんだろうか?と、首を傾げたくなります。そしてこのよう な埒もない質問にいちいちていねいに応える大人がいるいまの日本社会の平和 ボケに些か閉口、そして少しうすら寒いものを感じてしまいます。 新聞の塾の広告のフレーズ――「やる気と集中力」を育てる。 ほんとによく見かけるフレーズだが、ここにも「やる気」がなんの疑いもな く収まっていて、しかも「やる気と集中力」の2つを“育てる”というんだか ら、やる気と集中力のない、または乏しい生徒を持つ親御さんにはまことに有 難いお言葉に響くかも知れないけれど、果たしてどれだけ信用していいもので あろうか? わたしの場合、「やる気と集中力」をなんとか懸命に工夫して 「その場だけ」なら持たすことはできても、“育てる”なんてことは口が裂け てもいえない科白なのだが。 ちょっと考えればわかるではないか。小学校でまた中学校のこれまでで、ス ポーツではなく、あくまで勉強に限定しますが、子供に「やる気と集中力を育 ててもらった」とたしかに実感している、または感謝している先生にどれほど の方が巡り合ったのであろうか? 10人に1人もいるのだろうか? いやいや50 人に1人もいないのではないか・・・。その反対の良からぬ事例は昨今のニュ ースや新聞で数多あるわけだけど、それはさておき、なら塾の先生にそれを求 めることに一体なんの根拠があるのだろうか? 「〜を育てる」ということは、その育ったところまででいいから最低身につけ ていなければならないと思うのだが、塾で勉強のしかたと中身は教わったとし て、さらに平行して生徒本人に、感情に属しかつ恣意的な気分でもある「やる 気と集中力」を果たしてどれだけ身につけさせているのか、家でのその学習の 後姿から視てみればいいかと思いますね。数は少ないですが、もともと「やる 気と集中力」をもっている子は、それは他人の力によって育てられたものでは おそらくないでしょう。 もしわたしが、勉強に対して「やる気が出る方法はないでしょうか?」 なんて質問を受ければ、やる気のない気分、つまり返答したくない気分にはた と襲われて後退りしたくなってしまいますが、それでも万が一応えねばならな いことになったなら、逆にこうひとつ問いたい。 「やる気が出れば、勉強はスムーズに進むのか?!」と。 さて、ここからわたしが言いたいこと(ここから読んでいただいてもまった くいいくらいですが。) やる気が出てからようやく勉強ができると、多くの生徒は考えているようで すが、つまり、自分のなかにやる気が出てくるのを期待して待っているわけで すが、これほど当てにないならないものはないでしょう! なぜならそれは、 箍の外れた我儘な気分に過ぎないからですね。勉強は「気分」でやるものでは ない! ただ「習慣」でやるものだ! と、思います。 自分のなかにある、とりとめもない気分に甘えて流されるのではなく、昨日 したように、今日も同じようにするだけ。とり立てて考えるまでもなく、また 身構えて勉強に入っていくのではなく、ただただ習慣でやるものである。 やる気があろうがなかろうが、そんなことは関係ない。知ったことではない。 勉強に入っていけば、あとからやる気がじわっと出てくることなんてけっこう あるものです。また最初からやる気が大いにある場合にでも、勉強していく中 で却ってそれがギクシャクと空回りして、思い通りに進まず、つんのめる場合 もあるではありませんか。 勉強をこなす量も実は、その中身をみると、たとえば2時間やったとして、 前半の元気な1時間と後半のやや疲れたように感じる1時間を較べれば、それは 集中力の度合いにもよるのだけど、得てして後半の疲れた1時間の内容のほう が密度が濃い場合がしばしばあるでしょう。 もっといえば、3時間したあと、もういい、今日のノルマはじゅうぶん済ん だと感じたあとに、なんの弾みかさらに30分執念深く(?)粘り強く勉強した 結果に、疲労で雑になるかと思えば、逆に緻密な内容になっていることも意外 と多いものです。これらは、やる気から生まれるものではない。強いていえば、 ただ「習慣」である。そして「反復」である、と言えるのではないでしょうか? ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 上の内容とはかなり次元も角度・掘り下げ方も違うのだけど、この反復につ いて、参考になるかも知れませんので哲学的考察を下に書き記しておきます。 思想家、吉本隆明の言葉より。(ただし、実際のキルケゴールの使っている 「反復」と吉本隆明が解釈している「反復」とは、わたしが知る限りはだいぶ 異なっているのだけど、あくまで吉本隆明の表現が気に入っているもので。) ・キルケゴールの言葉でいえば、「反復というのが人間の本性に適してるとい うか、人間の本性は反復なんだ、あるいは人間の生涯は反復なんだということ でしょうか。時間は自然に過去から未来へと流れていくけど、人間の精神の時 間はかならず反復が繰り返されていく、人間の精神のもっている生涯のあり方 はそうなってる」 ・「人間の精神的な本性は反復で、ただ、時間は過去から未来へと流れていく けども、人間の精神は昨日あったことをまた明日、明後日にまたやるんだ。少 しずつは違うかもしれないけれども、反復です」 |
| ================================= 1.E-juku1st.Com の情報 NO.932<理科の勉強について> ================================= <勉強時間を増やさねば> 「理科の勉強のしかた」についてではなく、「理科の学力」についておそら く今後どういうことが予測されるか、そのすがたの内実と問題点について述べ てみることにします。 中学の5科目のなかで、ふだんの実力テストはもちろん、入試での平均点で 理科は、数学に並んで低い科目になるのがふつうかと思います。 入試では、理科のシビアな実力が出るということです。できる生徒はできる し、できない生徒はできない。どちらでもない真ん中あたりの生徒は、点数が 下がる。 そんななか対象を上位層の生徒に焦点をあて書きます、これはなにも理科に 限ってのことではありませんが、入試問題の内容が比較的やさしいとみんない い点数をとって差が出にくいものです。が、問題のレベルを意識的に上げると、 ほんとうの実力の差が、点数にすぐ反映されてくるものです。 成績がいい生徒のなかで、数・英・国の3教科はできても、理科と社会とな ると偏差値を下げている、また足を引っ張っている生徒は思いのほか多いです。 これは中1や中2のときはまだわからず、あるいは意識できず、というのは、学 校の定期テストでいい点数がとれているからに過ぎませんが、そして油断をし ているわけではまったくないにしてもたしかな実力として身につけていること とは必ずしも合致していないことが、中3になってようやくわかってくること が多いからです。 わかった段階でもっと勉強をすればいいことになりますが、しかし、このこ とはふつうのことで、個々の特殊なケースは除き、ふつうの努力結果に終わる こともまた多いのです。なんだか書いていることが抽象的すぎて意味がわかり づらいかと思いますので、数学と理科に限定して具体的に書きますと、たとえ ば次のようなイメージになります。数学はとても得意でかつ実力もある、しか し理科は上記のような生徒、とあえてここでは仮定します。わかりやすいよう にすべて100点満点とします。 ・数学:96点(定期テスト)、92点(中3実力テスト) →95点(その後の努力結果の実力テスト)、85点(入試点) ・理科:95点(定期テスト)、72点(中3実力テスト) →84点(その後の努力結果の実力テスト)、80点(入試点) これをどう読むかですね。どちらもふだんのテストではいい点数をとってお り似たようなものです。が、実力テストで大いに差が出ている。数学は努力結 果ですこし上がっているのに対し、理科はけっこう伸ばしている。いいではな いか、となりますが、たしかにいいのです。さて本番の入試での点数。数学は 85点でした。努力結果の実力より10点ダウンです。これが数学でしょう。コワ いです。しかし、この85点は、わたしからすればとてもすばらしくいい点数で す。 欲をいえば90点近くはとってほしかったですが、そのようにはいかないのが 数学です。これで正解です。さて、理科。努力結果の84点に対し、80点。実力 より4点低かったけれど、まずまずの点数がとれました。いいではないか、と いうことなのですが、はたしてそうか? たしかに中3実力テストの72点からよく努力し、成績は上がりました。立派 です。しかし、欲をいえばというか、理科と社会はもっと点数を確保しておき たいのです。公立トップ高を狙う生徒なら理科や社会は、入試で90点前後はで きるだけとりたいものです。 つまり、 「理科:95点(定期テスト)、88点(中3実力テスト)→95点(努力結果の実 力テスト)、90点(入試点)」 くらいの実力をつけておくのが、合格へのたしかな布石ではないかと思いま す。理科(と社会)の確かな学力は、ふだんのテストの結果だけではなかなか みえません。ほんとうの実力をつける勉強を、中1、中2からぜひ心掛けていっ てほしいと思っています。 |